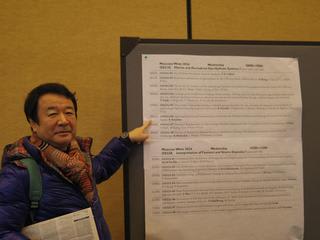▼東京の都心に、ある良心的な若手の和尚さんのいるお寺がある。
お坊さまに、若手、という表現はちと、変かな。
でも、実年齢は知らないけど、さらりと気負いなく戦っている、気さくなご住職で、まさしく「若手の和尚」さん、という感じなのだ。
先日、そこのお寺で、檀家さんたちや、和尚さんのお知り合いのみなさんを相手に、つたない講演をした。
和尚さんのご依頼は、「硫黄島の英霊や、沖縄の白梅の少女たちの話をしてほしい」ということだったから、ぼくは話し始める前から、すごく嬉しかった。
福島原子力災害が始まってから、みんなの不安に応えるためにも、話さねばならないことが増えすぎて、どの講演会でも、硫黄島の英霊のかたがたや、沖縄の白梅学徒看護隊の少女たちのことを話す時間が、まともに取れなくなって、胸のうちで、とても苦しかった。
だから、この若手の和尚さんの注文が嬉しくて、当日は、ぼくなりに懸命にお話をした。
司会は、なぜかインディペンデント・クラブ ( IDC/独立総合研究所に事務局のある会員制クラブ。ぼくと一緒に国会を訪ねたり、雪上集会といってスキーをしたり、いろいろな機会で一緒に勉強したり、考えたり、心と体を鍛えたりするクラブ )の女性会員の Y さんが務めてくれた。
この司会も素晴らしかった。Yさんは、わざわざ名古屋から来てくれた。最前列で、たくさん涙して、ぼくの、うまくもない話を聴いてくれた。
そして、若いひとから、働き盛り、高齢のかたまで、みなみなさまが、心を開くと言うより魂を開くように、熱心に聴いてくださった。
▼きょう、ニッポン放送のラジオ生番組「ザ・ボイス」に参加するために社有車の運転席に座ろうとしたとき、独研(独立総合研究所)の総務部から「あのお寺から、来年もお願いしますと依頼がありましたよ。来年は、チベットの話も頼みます、ということでした」と聞いた。
ぼくは、若手和尚さんの心意気を感じて、また嬉しかった。
すると、総務が「それで、社長、講演料なんですが…」と口に出した。
ぼくは、すこし驚いた。
なぜか。
独研の総務が、講演料はいくら、などといったことを、ぼくに伝えることはまず、ないからだ。
それは、講演を望まれるかたたちが、独研の総務部と調整することだ。そこで調整が完了することだ。
ぼくの財布には、講演料を1円も入れない。すべて独研に入れて、メタンハイドレートの調査研究費をはじめ、独研の運営資金にする。ぼくはとにかく、講演料の多寡 ( たか/多い少ない )にかかわらず、全身全霊で講演するだけだ。
どうして、今日に限って講演料の話をするのかと思ったら、その続きを聞いて、ぼくは仰天した。絶句した。
このお寺での、ことしの講演料と、来年の講演料の両方を、総務は教えてくれたけど、来年が、もの凄く高くなっている。
独研にとっては最高にありがたいことだけど、いったい、なぜ。
すると総務は「ことしは、このお寺は、講演仲介業者を通して、依頼してこられましたね。独研は、講演仲介業者には一切、頼んだりしていないことをお伝えしたので、来年については、直接、独研の総務部に言ってこられました。つまり、高くなった差額が、どうも業者に渡っていたようです」
その「差額」、すなわち、おそらくは仲介手数料というやつの高さに、ぼくは心の底から驚いた。あんまりにも、びっくり。
▼お寺の経営は決して楽じゃないでしょう。
ぼくに講演を頼むには、独研の公式HPにあるフォーマットに書き込んで送信するだけだ。ここです。
仲介料など、1円も、1銭も、かからない。
講演仲介業の方々の仕事を邪魔するつもりは、ゆめ、ありませぬ。
それはそれで、どうぞ頑張っていただきたいと思う。
しかし、そのビジネスは、講演仲介業者と契約を結んでいる講演者とご一緒に、なさるべきでしょう。
ぼくも、独研も、講演の仲介を頼んだことは一度たりともないし、これからも、決してない。
社長のぼくの講演だけではなく、自然科学部長の青山千春博士の講演であっても、まったく同じだ。
講演を望まれる、あるいは検討されているひとが、ぼくの名前を検索すると、自動的に、特定の講演仲介業者のサイトに飛ぶようになっている例もある。
そして、そのサイトでは「当社の講師一覧リスト」なんてのがあって、ぼくの名前が、一切なんの連絡も了解もないまま、まったく勝手に、載せられていたりする。
これは、すこし行き過ぎではありませぬか?
ぼくは、お抱え講師じゃない。
ぼくらは、何のしがらみもないから、「独立」総合研究所なんです。
講演を望まれる個人や会社などなどで、ふだんの講演仲介業のかたがたとのお付き合いとか、あるいはお金が余っている?とかで、どうしても講演仲介業者を通したいというかたがたは、もちろん、それでまったくOKです。
講演仲介業者から話が来たから断る、なんてことはしません。わたしたちは、何も分け隔てはしません。先ほども言ったように、講演仲介業者のお仕事の邪魔も、しません。
しかし同時に、どうぞ、自由に、いつでも、独研に直接、言ってきてください。
常に、どなたにも、窓を開いています。
上記の申し込みフォーマットに書き込んでいただくだけです。